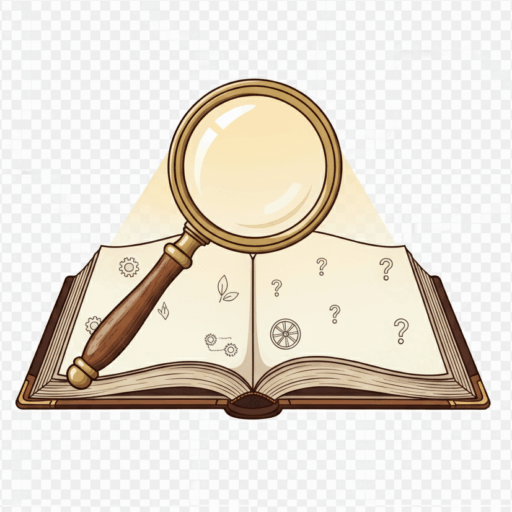I. 概要
現在進行中であるドナルド・トランプ大統領の第2期政権における主要な政策イニシアチブ、統治哲学、および国内外への影響について、包括的な分析を提供するものである。本政権の統治アプローチは、大統領府への権力集中と連邦政府の官僚機構に対する政治的統制の確立を目的とする「プロジェクト2025」にその思想的基盤を見出すことができる。この枠組みは、政権の行動を理解する上で不可欠な青写真として機能している。
政権の政策は、主に3つの柱によって構成されている。第一に、普遍的関税の導入と追加減税を組み合わせた、抜本的な経済的再編である。この政策は、国内製造業の回帰と投資の活性化を目指す一方で、世界的な貿易秩序に大きな変動をもたらし、インフレ圧力と消費者コストの上昇に関する深刻な懸念を引き起こしている。第二に、移民政策、規制緩和、司法制度の再構築を主眼とした、広範な国内改革である。特に移民政策においては、国家安全保障を名目とした強硬な執行措置が取られており、法的な論争を巻き起こしている。第三に、「アメリカ・ファースト」外交政策の強化である。これは、多国間主義からの後退と、同盟国との関係を取引的なものへと変容させ、米国の伝統的な国際的役割を再定義するものである。
本政権の統治スタイルは、議会を迂回した大統領令の多用、政策目標達成のための取引的アプローチ、そして国内および国際情勢に著しい不確実性をもたらすハイリスク・ハイリターンな戦略によって特徴づけられる。本報告書は、これらの政策がもたらす多面的な影響を詳細に検証し、今後の戦略立案に資する客観的な情報を提供することを目的とする。
II. 構造的枠組み:プロジェクト2025の解体
第2次トランプ政権の政策を単なる個別の提案の集合体としてではなく、その根底にある思想的・運用的青写真として理解するためには、「プロジェクト2025」の分析が不可欠である。このプロジェクトは、大統領府に行政権を統合し、アメリカ政府の構造そのものを体系的に再構築することを目的とした詳細な計画である。
イデオロギー的基盤:単一行政官理論
プロジェクト2025の法的・思想的な支柱となっているのは、「単一行政官理論」の急進的な解釈である。この理論は、合衆国憲法第2条に基づき、行政府の完全な統制権が大統領一人に帰属すると主張する [Project 2025 – Wikipedia]。伝統的な権力分立や、専門性に基づいて一定の独立性を保ってきた行政機関の役割を根本から覆し、大統領の意向が直接かつ迅速に連邦政府の隅々まで行き渡る統治体制の構築を目指すものである。
人事は政策なり:公務員制度の再構築
プロジェクト2025の最も核心的な戦略の一つが、能力主義に基づく数万人の連邦公務員を、政権の政策課題への忠誠心に基づいて事前に選抜された人材へと置き換える計画である [How Trump’s policies and Project 2025 proposals match up after first 100 days – CBS News]。
独立機関の政治化
伝統的に党派的な影響から距離を置いてきた機関に対しても、政治的な統制を及ぼそうとする動きが顕著である。その象徴的な例が、労働統計局(BLS)への介入である。政権がBLSの発表する雇用統計データを批判した後、プロジェクト2025の共著者であり、保守系シンクタンクであるヘリテージ財団のエコノミスト、E.J. アントニ氏を次期局長に指名した [Labor statistics chief fired by Trump sounds alarm over White House’s ‘dangerous’ interference]。この人事は、批判者から「経済データへの干渉」であり、主要な経済指標の信頼性を損なう試みであると厳しく批判されている [Labor statistics chief fired by Trump sounds alarm over White House’s ‘dangerous’ interference]。
この一連の動きは、単に個別の政策を変更するというレベルを超えている。政権の目標は、政府という機械そのものを再設計することにある。人事、組織構造、さらには政策決定の基礎となるデータの信頼性にまで介入することで、政権の急進的な政策課題の迅速な実行を妨げる可能性のある制度的障壁を取り除くという戦略的な意図がうかがえる。これは、大統領の指令に対して「ディープステート(国家の内部国家)」が抵抗したり、その実行を遅らせたりすることを不可能にすることを目指している。その結果、行政府は内部のチェック・アンド・バランス機能に制約されることなく、より強力な権限を大統領に集中させることになる。これは、統治の継続性、制度的記憶、そして権力分立の原則そのものに長期的な影響を及ぼす可能性がある。
III. 第一の柱:「アメリカ・ファースト」経済再編
本政権の経済戦略は、保護主義的な貿易体制と、規制緩和および低税率を特徴とする財政政策という、2つの主要な要素から構成されている。前者は製造業の国内回帰と貿易赤字の削減を、後者は国内投資の刺激をそれぞれ目的としており、これらが一体となって「アメリカ・ファースト」経済の実現を目指すものである。
A. 普遍的関税レジーム:世界貿易フローの再構築
第2次トランプ政権は、特定の品目や国を対象とした従来の関税政策から一歩踏み込み、世界的な貿易障壁システムを構築するという、より攻撃的なアプローチを採用している。関税は、経済政策の主要なツールであると同時に、外交政策を遂行するための強力な武器としても位置づけられている。
主な提案と実施
政権は、全ての輸入品に対して10%から20%の範囲で普遍的な基準関税を課すことを提案している [REMINDER: Trump’s Disastrous Project 2025 Economic Agenda Would Raise Costs on Michigan Families – Democrats.org]。これに加えて、特定の戦略的競合国に対しては、はるかに高い関税が設定される。特に中国からの全輸入品に対しては、60%以上という極めて高い関税率が提案されている [The Five_stars’s Profile | Binance Square]。
スコット・ベッセント財務長官が主導するこの計画の実施は、段階的に行われる設計となっている。まず全ての輸入品に2.5%の関税を課し、その後、目標である20%に達するまで毎月税率を引き上げていく [EUR/USD tumbles as USD’s appeal strengthens on DeepSeek concerns – Inveslo]。この段階的なアプローチは、米国が貿易相手国との交渉において優位な立場を確保するための戦略的な措置であるとされている [EUR/USD tumbles as USD’s appeal strengthens on DeepSeek concerns – Inveslo]。
最初の標的として、乗用車、医薬品、半導体、鉄鋼、アルミニウムといった品目に対して25%の関税が課される予定であり、早ければ2025年の3月から4月にかけて発効する見込みである [Keeping track of Trump’s tariff threats: The countries, the products …]。
公言されている論理的根拠
政権は、関税が米国の産業を保護し、国内製造業を復活させ、貿易赤字を削減し、特に中国による不公正な貿易慣行に対抗するための不可欠な手段であると主張している [The Five_stars’s Profile | Binance Square]。トランプ大統領自身、関税を「我が国の兵器庫における最大の交渉ツール」と表現している [The Five_stars’s Profile | Binance Square]。この考え方の根底には、貿易を国家安全保障と経済的自立の観点から捉え、自由貿易よりも保護主義を優先するという思想がある。
経済的影響と市場の反応
この急進的な関税政策は、国内外の経済に多大な影響を与え、市場に大きな不確実性をもたらしている。
- 消費者コスト:複数の分析が、関税によるコスト増は最終的に消費者に転嫁されると予測している。タックス・ファウンデーションの試算によれば、メキシコ、カナダ、中国からの輸入品に対する関税だけで、2025年には米国の平均的な世帯で年間830ドル以上の税負担増になるとされている [Keeping track of Trump’s tariff threats: The countries, the products …]。ピーターソン国際経済研究所はさらに踏み込み、普遍的関税計画によって平均的な世帯の負担は年間1,500ドルから2,000ドル増加する可能性があると予測している [The Five_stars’s Profile | Binance Square]。
- インフレ圧力:16人のノーベル賞受賞経済学者が、この関税計画は「インフレを再燃させ」、世界経済に長期的な害を及ぼすと警告している [REMINDER: Trump’s Disastrous Project 2025 Economic Agenda Would Raise Costs on Michigan Families – Democrats.org]。市場アナリストも同様に、インフレの急騰と市場の不安定化を懸念している [The Five_stars’s Profile | Binance Square]。
- ビジネスおよびセクターへの影響:国内の鉄鋼・アルミニウム生産者など一部の業界は恩恵を受ける可能性があるが [The Five_stars’s Profile | Binance Square]、輸入部品に依存する多くの業界、特に小売、テクノロジー、自動車メーカーは、サプライチェーンの混乱と利益率の圧迫という深刻な課題に直面している [The Five_stars’s Profile | Binance Square]。拡大された鉄鋼・アルミニウム関税だけでも、17,000人分のフルタイム雇用が失われると予測されている [Keeping track of Trump’s tariff threats: The countries, the products …]。
- 国際的な反応:この政策はすでに、特に中国からの報復関税を引き起こしている。また、EUや韓国などの同盟国は、関税の適用除外を求める交渉を余儀なくされている [Keeping track of Trump’s tariff threats: The countries, the products …]。この不確実性は、安全資産としての米ドルの魅力を高め、結果としてEUR/USDなどの通貨ペアが下落する一因となっている [EUR/USD tumbles as USD’s appeal strengthens on DeepSeek concerns – Inveslo]。
この関税レジームの適用は、従来の貿易保護主義の範疇を大きく超えている。政権は、関税を非経済的な目標を達成するための多目的かつ強制的な手段として利用しており、これは米国の対外関係の性質を根本的に変容させるものである。その運用は、単なる貿易収支の是正にとどまらない。例えば、政権はコロンビアに対して、国外追放された同国人の受け入れを強制するために、関税の脅威を利用した。これは、貿易政策を移民法の執行と直接結びつけるものである [The Return of ‘America First’: How the 2024 election redefines the United States – Indian Review of Global Affairs]。さらに、トランプ大統領は、デンマークからのグリーンランド買収やパナマからのパナマ運河の支配権獲得といった領土的な野心を推進するために関税を利用する可能性を公に示唆している [Keeping track of Trump’s tariff threats: The countries, the products …]。
これらの事例は、関税がもはや単なる経済政策ではなく、議会の承認や伝統的な外交プロセスを経ることなく、移民問題から領土拡大に至るまで、広範な問題について他国に米国の要求を飲ませるための、大統領に集中化された権力ツールとして機能していることを示している。これにより、米国の貿易関係は、相互利益に基づくパートナーシップから、米市場へのアクセスが、広範で予測不可能な米国の要求への準拠を条件とする、取引的でしばしば敵対的な関係へと変貌しつつある。
B. 「減税2.0」:財政戦略と分配効果
「減税2.0」は、第1期政権で制定された減税措置を恒久化し、さらに拡充することを目的とした、本政権の看板となる国内経済政策である。2025年2月に下院で予算決議として可決されたこの法案は、政権の経済成長戦略の中核をなすものである [Trump Tax Cuts 2.0 – MMG Real Estate Advisors]。
主な法案提案
この減税パッケージは、個人および法人に対する広範な税負担軽減策を含んでいる。
- TCJAの恒久化:2025年末に失効予定だった2017年の「減税・雇用法(TCJA)」における個人所得税減税を恒久化する [Trump Tax Cuts 2.0 – MMG Real Estate Advisors]。
- 法人税率の引き下げ:一般法人税率を現行の21%から20%に引き下げる [Trump Tax Cuts 2.0 – MMG Real Estate Advisors]。さらに、米国内で製品を製造する企業に対しては、税率を15%まで引き下げるという的を絞った優遇措置も提案されている [Trump Tax Cuts 2.0 – MMG Real Estate Advisors]。
- 新たな個人向け免税措置:ポピュリズム的なアピールを狙い、チップ、残業代、社会保障給付金に対する連邦所得税を撤廃する [Trump Tax Cuts 2.0 – MMG Real Estate Advisors]。
- キャピタルゲインとSALT控除:高所得者層のキャピタルゲイン税の最高税率を20%から15%に引き下げ、州・地方税(SALT)控除の上限である10,000ドルを撤廃する [Trump Tax Cuts 2.0 – MMG Real Estate Advisors]。
経済および予算への予測される影響
この大規模な減税計画は、経済成長を促進するという期待と、財政赤字の拡大や格差の助長という懸念の両面から、激しい議論を呼んでいる。
- 成長促進論:支持者たちは、この減税が労働と投資へのインセンティブを高めることで、2026年から2027年にかけて年間GDPを0.5%押し上げると予測している。そして、その結果としての経済成長が課税所得を増加させ、最終的には連邦政府の歳入を押し上げる可能性があると主張している [Trump Tax Cuts 2.0 – MMG Real Estate Advisors]。
- 赤字と格差への懸念:批判的な立場からは、この計画が富裕層と大企業を不釣り合いに優遇し、経済格差をさらに拡大させるとの指摘がなされている [REMINDER: Trump’s Disastrous Project 2025 Economic Agenda Would Leave Nevada Families Behind – Democratic Party]。事実、2017年の減税は、億万長者が労働者階級よりも低い税率で済む状況を生み出したとの分析もある [REMINDER: Trump’s Disastrous Project 2025 Economic Agenda Would Raise Costs on Michigan Families – Democrats.org]。減税の恒久化は国家の財政赤字を悪化させ [Trump Tax Cuts 2.0 – MMG Real Estate Advisors]、その穴埋めのためにメディケイド(低所得者向け医療保険制度)のような社会保障プログラムの削減が強いられる可能性があると懸念されている [Trump Administration (Executive Session); Congressional Record Vol. 171, No. 15 (Senate – January 24, 2025) – Congress.gov]。法人税率をわずか1%引き下げるだけで、著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏の個人資産が46億ドル増加するという試算もあり、減税の恩恵が極めて偏っていることを示唆している [Trump’s Tax Cuts 2.0 Are Just More of a Bad Thing – Patriotic Millionaires]。
表1:「減税2.0」の主要規定の概要
| 政策分野 | 現行法(2.0以前) | 「減税2.0」における変更案 | 公言されている論理的根拠/対象者 |
|---|---|---|---|
| 個人所得税 | TCJA税率が2025年以降失効 | TCJA税率の恒久化 | 個人に対する税制の安定性を提供 |
| 新たな免税措置 | チップ、残業代、社会保障給付金は課税対象 | チップ、残業代、社会保障給付金を連邦所得税から免除 | サービス業従事者、中間所得層、高齢者に恩恵 |
| 法人税 | 21%のフラットレート | 一般税率を20%に引き下げ、国内製造業者には15%を適用 | 米国の競争力を強化し、国内回帰を奨励 |
| キャピタルゲイン税 | 最高税率20% | 最高税率を15%に引き下げ | 投資を奨励 |
| SALT控除 | 10,000ドルが上限 | 10,000ドルの上限を撤廃 | 高税率州の納税者の負担を軽減 |
政権の経済政策には、根本的な矛盾が存在する。一方で、チップや残業代の非課税化といった的を絞った減税策を通じて、労働者階級の有権者にアピールしようとしている。しかし、その一方で、減税パッケージ全体の枠組みは、最も裕福なアメリカ人と大企業に不釣り合いな利益をもたらすように設計されている。これは、経済的利害が異なる複数の集団からなる、脆弱な支持連合を築き上げようとする複雑な政治戦略を明らかにしている。
チップ、残業代、社会保障給付金を非課税にするという提案は、明らかに中間層および労働者階級の有権者をターゲットにしている [Trump Tax Cuts 2.0 – MMG Real Estate Advisors]。これらはシンプルで具体的な利益であり、ポピュリスト的なメッセージと共鳴しやすい。しかし、「減税2.0」パッケージの核心部分、すなわちTCJAの恒久化、法人税率の引き下げ、キャピタルゲイン減税、SALT控除上限の撤廃は、高所得世帯と法人を優遇するものであると広く分析されている [How Project 2025’s Economic Policies Hurt Families]。
この構造は、政策内に緊張を生み出している。富裕層に利益をもたらす大規模な減税のコストは、国家債務を増加させることが予測されており [Trump Tax Cuts 2.0 – MMG Real Estate Advisors]、批判者たちは、その負担は最終的に低所得世帯向けのメディケイドのようなプログラムの削減によって賄われることになると主張している [Trump Administration (Executive Session); Congressional Record Vol. 171, No. 15 (Senate – January 24, 2025) – Congress.gov]。したがって、労働者向けの小規模で的を絞った減税は、パッケージ全体の、はるかに大規模で逆進的な影響を覆い隠すための政治的な「甘味料」と見なすことができる [A Real Tax Cut for Working Americans: Repealing and Replacing the Payroll Tax – Progressive Policy Institute]。政権は、有権者が直接的で目に見える利益(チップへの非課税)に注目し、間接的で体系的な結果(社会サービスの削減の可能性や富の格差拡大)を見過ごすことに賭けているのである。
IV. 第二の柱:国内改革アジェンダ
第2次トランプ政権は、移民法の執行、社会的・環境的規制の撤廃、そして連邦司法府の継続的な再構築という、野心的な国内政策を強力に推進している。これらの政策は、米国の社会構造と法制度に大きな変革をもたらすことを意図している。
A. 移民、国境警備、および法執行
政権は発足当初から、移民問題への強硬な対応を最優先課題として掲げ、これまでにない攻撃的な法的戦術を駆使している。
大規模強制送還戦略
政権は、1798年に制定された「外国人敵国人法」を発動し、特にベネズエラからの移民を国家安全保障上の脅威と分類することで、大規模な強制送還を容易にする道を開いた [The Return of ‘America First’: How the 2024 election redefines the United States – Indian Review of Global Affairs]。この法律の適用は、現代の移民法が定める多くの手続き要件を迂回するものであり、法的な正当性を巡って激しい論争を呼んでいる。
大統領令による措置
一連の大統領令を通じて、全ての不法滞在移民の強制送還を迅速化し、国境地帯に追加の連邦部隊を展開させ、亡命申請の受付を全面的に停止する措置が講じられた [The Return of ‘America First’: How the 2024 election redefines the United States – Indian Review of Global Affairs]。これにより、国境管理は事実上、人道的な配慮よりも法執行と安全保障を最優先する体制へと移行した。
強制的な外交
前述の通り、関税の脅威は外交上の圧力手段としても利用されている。コロンビア政府に対し、強制送還される自国民の受け入れを承諾させるために、厳しい関税を課す可能性が示唆されたのはその一例である [The Return of ‘America First’: How the 2024 election redefines the United States – Indian Review of Global Affairs]。これは、貿易政策と移民政策を直接連動させ、他国に米国の政策への協力を強いるという、取引的な外交姿勢を象徴している。
1798年の「外国人敵国人法」への回帰は、移民問題を従来の民事行政手続きの範疇から、国家安全保障と大統領の戦争権限の問題へと移行させるという、戦略的な法的転換を意味する。このアプローチにより、行政府は非常時の権限を主張し、移民に対して確立されてきた法的保護を回避することが可能になる。通常の強制送還手続きは、聴聞の権利や適正手続きを含む「移民国籍法」に基づいて行われる。これらの手続きは時間がかかり、司法審査の対象となる。しかし、「外国人敵国人法」は戦時下の法律であり、敵国の国民を拘束し、国外追放する広範な権限を大統領に与えるものである [The Return of ‘America First’: How the 2024 election redefines the United States – Indian Review of Global Affairs]。
この法律を発動し、移民を国家安全保障上の脅威と位置づけることで、政権は法執行活動を伝統的な移民法の枠組みから、大統領の戦争権限の領域へと移そうと試みている。これは、対象となる個人の適正手続きの権利を剥奪し、前例のない規模で強制送還を加速させ、民事裁判所での異議申し立てを困難にする可能性がある。これは移民政策の急進化であり、人口動態や経済の問題から、国家防衛の問題へとその定義を根本的に変えるものである。
B. 規制緩和と連邦司法府
政権は、大統領令による特定の規制の撤廃と、連邦政府の規制権限を制限する司法哲学を持つ裁判官の任命という、二重の戦略を追求している。
DEIおよび環境保護の解体
- 政権発足初日、大統領は連邦政府内の全ての「多様性、公平性、包摂性(DEI)」プログラムを終了させる大統領令に署名した [How Trump’s policies and Project 2025 proposals match up after first 100 days – CBS News]。さらにプロジェクト2025は、「DEI」「中絶」「ジェンダー平等」といった用語を、全ての連邦規則や規制から削除することを求めている [How Trump’s policies and Project 2025 proposals match up after first 100 days – CBS News]。
- 環境分野では、化石燃料を優遇するために環境規制を緩和し [How Project 2025’s Economic Policies Hurt Families]。
司法官任命:より遅く、より論争的な道
- 第2期政権における連邦裁判官の任命ペースは、第1期に比べて大幅に遅れている。最初の7ヶ月間で承認された裁判官はわずか5人にとどまっている [Trump Says His Constitutional Right to Appoint Judges Being Denied – Newsweek]。
- 大きな障害となっているのが、上院の「ブルースリップ」慣行である。これは、選挙区選出の上院議員(特に野党議員)が、その州の連邦地方裁判所判事候補の承認に対して事実上の拒否権を持つことを可能にするものである。大統領はこの慣行を公に非難し、その撤廃を要求している [Trump Says His Constitutional Right to Appoint Judges Being Denied – Newsweek]。
- 政権は最終的に連邦控訴裁判所の多数派を共和党指名判事で占めることに成功するかもしれないが、より多くの判事を擁する連邦地方裁判所において、2029年までに同様の多数派を形成することは困難であると見られている [How much will Trump’s second-term judicial appointments shift court …]。
シェブロン原則廃止後の法的状況
連邦最高裁判所が「シェブロン原則」を覆したことは、法曹界に大きな変化をもたらした。この原則は、法律の条文が曖昧な場合、裁判所は管轄省庁の専門的な法解釈を尊重すべきであるというものであった。その廃止は、規制国家の権限を弱めたい政権の目標と一致する。しかし、皮肉なことに、これは政権自身の行動を妨げる要因にもなり得る。政権の反対派が、特定の裁判官を狙って訴訟を起こす「フォーラム・ショッピング」を通じて、政権の大統領令を差し止めることが、以前よりも容易になる可能性があるからである [Will the Supreme Court’s Chevron decision undercut Trump’s unilateral presidency?]。
政権の政策には、重大な緊張関係が存在する。プロジェクト2025が目指す最大限の大統領権限の行使という目標と、シェブロン原則の廃止に象徴される、行政府の権威を弱める司法哲学の支持という目標が、互いに矛盾しているのである。この結果、政権が自ら推進しようとしている政策課題が、自らが形成しようとしている裁判所によって妨げられるという事態が生じかねない。プロジェクト2025の単一行政官理論は、大統領が一方的に行動する権限を最大化することを目的としている [Will the Supreme Court’s Chevron decision undercut Trump’s unilateral presidency?]、その実際的な効果として、裁判官はもはや省庁の法解釈に拘束される必要がなくなった。これにより、個々の裁判官が自らの判断を優先させることが可能になる。政権の反対派は、政権の政策に思想的に反対する民主党指名の裁判官がいる裁判管区で訴訟を起こすことができ、実際にそうしている [Will the Supreme Court’s Chevron decision undercut Trump’s unilateral presidency?]。シェブロン原則がなければ、これらの裁判官は、大統領令を差し止める全国的な差止命令を出す権限をより強力に持つことになる。したがって、保守派にとっての法的な勝利が、攻撃的な大統領令を通じて統治しようとする保守派大統領にとって、大きな実践的障害となり得るのである。
V. 第三の柱:取引的な世界における外交政策
第2期政権の外交政策は、「アメリカ・ファースト」ドクトリンの強化、多国間主義への深い懐疑、そして一方的かつ強制的な行動の選好によって特徴づけられる。これは、第1期からの継続であると同時に、そのアプローチをさらに先鋭化させたものである。
「アメリカ・ファースト」2.0:取引的かつ一方的
政権の外交アプローチは、「露骨で公然と強制的な米国の力の投影」と評されている [The Historical Architecture of U.S. Hegemony: Trump’s Second Term and the Evolution of Coercive Power,]。これは孤立主義ではなく、むしろ一方的な介入主義の一形態である [The Historical Architecture of U.S. Hegemony: Trump’s Second Term and the Evolution of Coercive Power]。
- 伝統的な同盟国との関係は、取引的かつしばしば敵対的なものとなっている。経済的な関税の脅威が、影響力を行使するための主要な手段として用いられている [Second presidency of Donald Trump – Wikipedia]。政権は、NATO同盟国に対して防衛費の増額を求め続け、目標を達成できない国を防衛しない可能性を示唆している [Second presidency of Donald Trump – Wikipedia]。
- 外交政策の中心的な目標は、中国の影響力を封じ込めることにある [Second presidency of Donald Trump – Wikipedia]。米中関係は、経済、技術、軍事の各分野で、より一層の対立的な様相を呈している。
グローバル・ガバナンスからの後退
政権は、国際的な枠組みや機関から距離を置く姿勢を鮮明にしている。
- 世界保健機関(WHO)、気候変動に関するパリ協定、国連教育科学文化機関(UNESCO)からの米国の脱退手続きを開始した [Second presidency of Donald Trump – Wikipedia]。
- 米国国際開発庁(USAID)が管轄するほとんどの対外援助プロジェクトは中断され、国務省および中央情報局(CIA)では、政権に忠実な人物を配置するための大幅な人事異動が行われた [Trump’s Second-Term Foreign Policy: Highly Centralized, and …]。
拡張主義的な言説
第2期政権では、一部のアナリストが「新アメリカ帝国主義」と呼ぶような、拡張主義的な傾向が見られる [Trump’s Second-Term Foreign Policy: Highly Centralized, and …]。これは、トランプ大統領が公言した、グリーンランドの買収、必要であれば武力を行使してでもパナマ運河の支配権を回復すること、そしてカナダを米国に併合する可能性といった発言に表れている [Trump’s Second-Term Foreign Policy: Highly Centralized, and …]。
政権の外交政策は、グローバル・ガバナンスにおける力の空白を生み出し、その隙を戦略的なライバル国が積極的に埋めようとしている。同時に、米国の伝統的な同盟国に対しては、戦略的な自立を加速させる結果を招いている。「アメリカ・ファースト」政策は、意図せずして、ポスト・アメリカ的な世界秩序の到来を早めている可能性がある。米国がWHOのような主要な国際機関から脱退し、多国間協調の枠組みを放棄することで [Second presidency of Donald Trump – Wikipedia]、これらの機関内での米国のリーダーシップと影響力は低下する。アナリストは、この空白をロシアと中国が埋めていると指摘している [Second presidency of Donald Trump – Wikipedia]。これらのライバル国は、内部からの米国の反対なしに、自国に有利な形で国際的な規範や制度を形成することが可能になる。
同時に、欧州の同盟国に対する政権の取引的で信頼性の低い姿勢は、欧州の再軍備と戦略的自立への動きを加速させている [Second presidency of Donald Trump – Wikipedia]。同盟国は、もはや自国の安全保障を米国だけに依存することはできないと結論付けつつある。したがって、「アメリカ・ファースト」政策の長期的かつ意図せざる結果は、米国主導の国際システムの侵食である。自国の行動の自由を最大化しようとすることで、政権は同盟国と敵対国の双方に、米国への依存度が低く、かつ米国にとって有利とは言えない世界の構築を促しているのである。
VI. セクター別影響分析と今後の見通し
本章では、第2次トランプ政権の政策が主要な産業セクターに与える影響を統合的に分析し、この統治アジェンダから生じる主要なリスクと戦略的課題について、将来を見据えた評価を行う。
エネルギーと環境
環境規制の緩和とパリ協定からの離脱 [Project 2025 – Wikipedia]、そして石炭火力発電にとって有利な規制環境の整備 [2024 Investor Presentation Bringing Natural Resources to Life] は、エネルギー政策が化石燃料へと大きく回帰していることを示している。米国エネルギー情報局(EIA)が予測する2025年および2026年の電力消費量の増加は、石炭のような24時間稼働可能なベースロード電源の必要性を正当化する根拠として利用されている [2024 Investor Presentation Bringing Natural Resources to Life]。この政策転換は、再生可能エネルギーセクターの成長を鈍化させ、米国の気候変動目標の達成を著しく困難にするだろう。
貿易と製造業
普遍的関税レジームは、国内産業に明確な勝者と敗者を生み出している。鉄鋼やアルミニウムのように保護された産品の国内生産者は、短期的な利益を得る可能性がある [The Five_stars’s Profile | Binance Square]。しかし、自動車、テクノロジー、小売といったグローバルなサプライチェーンに深く依存する産業は、深刻な混乱とコスト増に直面している [The Five_stars’s Profile | Binance Square]。この政策の長期的な成否は、大規模な製造業の国内回帰(リショアリング)を本当に実現できるかどうかにかかっているが、これは経済的な混乱を伴う可能性のある、極めてリスクの高い賭けである。
今後の見通し:主要な摩擦点
- 経済の不安定性:政権の経済政策は、関税がもたらすインフレ効果と、減税による景気刺激効果という、相反する力の間に存在する。貿易戦争が引き起こす景気後退のリスクは、増大する国家債務と相まって、依然として最大の経済的脆弱性である。
- 制度的ストレス:プロジェクト2025の実行は、司法府、公務員制度、そして州政府との間で継続的な対立を生み出すだろう。これにより、法廷闘争が頻発し、統治機能が麻痺する可能性がある。制度的なチェック・アンド・バランスがどこまで機能するかが、今後の米国のガバナンスの安定性を左右する。
- 世界的な地政学的リスク:多国間主義からの後退と、同盟国に対する取引的なアプローチは、戦略的な敵対国を勢いづかせ、地域紛争のリスクを高める可能性が高い。紛争が発生した場合、米国は信頼できるパートナーが以前よりも少ない状況で対応を迫られるかもしれない。政権の政策は、世界秩序を積極的に再構築しており、その新しい秩序がどのような形になるのかは、依然として危険なほど不透明である。